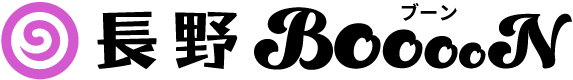神楽坂が大好きな人の[神楽坂 de かぐらむら]
【サイトからのお知らせ】
ESSAY
かぐらびと
- 全て
- 神楽坂の新店
- 神楽坂の人気店
- 神楽坂の老舗
-
かぐらびと 神楽坂の新店
2026.02.18
【開店】早稲田で31年の名店、その系譜を神楽坂へ | 焼鳥あかぎ
by かぐらむら編集局
-
かぐらびと 神楽坂の新店
2025.11.26
東京初!本格ジョージア料理&ワインバー|AJIKA
by かぐらむら編集局
-
かぐらびと 神楽坂の人気店
2025.10.22
牧場直営!繊細な口どけと旨味のブランド和牛 | ふらの和牛 よしうし 神楽坂通り
by かぐらむら編集局
-
かぐらびと
2025.09.17
花と暮らしをデザインする、フラワーアレンジメントサロン | Salon de Lilas(サロンドリラ)
by かぐらむら編集局
-
かぐらびと 神楽坂の人気店
2025.08.27
山梨ワイナリー直送ワイン&カジュアルフレンチ | 神楽坂ルバイヤート
by かぐらむら編集局
-
かぐらびと 神楽坂の新店
2025.07.30
【開店】親から子へつなぐ、大館曲げわっぱ | 柴田慶信商店
by かぐらむら編集局
おやびん劇場
MODEL COURSE
モデルコース
TOPICS
今月の指定席
EVENT
催事・イベント
-
-
-
矢来・横寺 伝統芸能2026.03.01(日)
【全席完売】第36回としま能の会 -妖怪と精霊-
公益財団法人としま未来文化財団設立40周年記念事業 「としま能の会」が3年ぶりに復活!36回目となる今回は、「妖怪と精霊」をテーマに開催します。 能楽堂での初開催をお見逃しなく! 日程:2026年3月1日(日曜) 開演時間 昼の部:13時00分開演(12時30分開場) 狂言「蚊相撲」 能「殺生石 白頭」 (演目解説あり) 夜の部:17時00分開演(16時30分開場) 狂言「蟹山伏」 能「鞍馬天狗」 (演目解説あり) 出演 観世喜正(シテ方観世流)ほか ※昼夜で出演者が異なります チケットは全席完売 料金:全席指定(税込/昼夜入替制) S席…正面席 A席…脇正面席/中正面席 【一般】S席:4,800円、A席:4.300円 【豊島区民割引】S席:4,500円、A席:4,000円(としまチケットセンターのみ取扱) 【学生】S席:2,000円、A席1,500円 【昼夜通し】S席:8,800円、A席:7,800円(としまチケットセンターのみ取扱) ※未就学児入場不可 ※豊島区民割…豊島区在住/在勤/在学対象 ※学生券は公演当日25歳以下の方対象(要学生証提示) チケット取扱い ●としまチケットセンター 【電話】 0570-056-777(10時から17時/臨時休業あり) 【WEB】 ページ下の「インターネットお申込み」ボタン(発売日よりページ下部に表示)より申込。(24時間受付) 【窓口】 豊島区東池袋1-20-10 としま区民センター1F(10時から19時/臨時休業あり) ●イープラス 【WEB】 http://eplus.jp/ 【店頭】 ファミリーマート 注意事項 ※車椅子でご来場の方は、事前にとしまチケットセンターへお問合せください。 ※開演後にご来場いただいた場合は、客席へご案内できない時間帯がございます。 ※やむを得ない事情により、イベントの中止または内容の変更が生じる場合がございます。
-
-
-
-
飯田橋界隈 お店の催し2026.03.01(日)
受付終了【東京大神宮】雛まつりの祓
縁結びの神社に願いを託すひな祭り 今年も東京大神宮で無病息災と心願成就を祈願する「雛まつりの祓」が執り行われます。 祈願の後には特別奉製の「ひな守」と記念品が授与されます。境内では2月4日から3月3日まで、願いごとが書き込める「雛まつり形代(初穂料300円)」が授与されますので、願いごとを託して納め箱へお納めください。 2/27更新雛まつりの祓 申込終了いたしました。 ※2月4日(水)から、公式サイトでお申し込みください。 ※事前予約制です。申込期間内でも定員に達し次第締切となります。
-
-
-
-
赤城・水道 祭り2026.03.01(日)
【赤城神社】令和八年三月 月次祭
【赤城神社 月次祭】 令和八年三月一日斎行 月初めに行われる、 その月の平穏を願うお祭りです。 どなたさまもご参列になれます。 氏神様に日頃の感謝を伝え、皇室の方々、氏子、崇敬者、 ひいては日本国民が何事もなく、豊かに暮らせるよう、祈りを捧げます。 大きな神社ではほぼ全て行われているものの、一般の参列者を募っていないところも多く、 逆に小さな神社では様々な理由により、お祭りが行えていないところもございます。 赤城神社ではこのような「恒例祭(こうれいさい...周期的に行われるお祭り)」に 参列を希望する方々が昇殿して参拝することができます。 月次祭のご参列はご予約不要です。お時間までに拝殿へお越しください。 ぜひ、お気軽にご参拝ください。 【ご参列について】 ・ご予約は不要です ・お時間までに拝殿へお越しください ・ご参列は自由に行えます ・初穂料は1,000円です※授与品あり 開催日や時間は以下からご連絡いたします。ぜひ、ご登録ください。 【赤城神社からのメールでお知らせ】 1 . こちらからメールアドレスを登録 2 . 毎月届くご案内メールをご確認 【X(旧twitter)でお知らせ】 1.赤城神社公式アカウントをフォロー https://twitter.com/Akagi_Jinja_ 2.月次祭に関する投稿をチェック
-
-
-
-
矢来・横寺 お店の催し2026.02.28(土)~03.04(水)
【入場無料】バーンロムサイジャパン banromsai @神楽坂
春をまとう、banromsaiの服 ―― やさしい素材と、物語をまとう時間 ―― ガーゼやリネンなど、肌にすっとなじむ着心地の良い素材で知られるbanromsaiに、春の新作が加わりました。 今季は、日本の春に心地よく寄り添う新作に加え、タイ・チェンマイのアトリエから届いた最新アイテムもお披露目。 軽やかで風をはらむようなシルエットと、日常の動きに自然に寄り添う仕立てが印象的です。 会期中はあわせて、ビンテージアイテムや一点ものの参考商品が並ぶGarage Saleも開催。 今では出会えない素材感やデザインなど、思いがけない“掘り出しもの”との出会いもお楽しみいただけます。 装うことが、少しだけ暮らしを整え、気持ちをやわらかくしてくれる——そんなbanromsaiらしい時間を、ぜひご体感ください。 ■アーティストプロフィール 2001年から始まったbanromsaiのものづくり。 タイ・チェンマイにあるBan Rom Sai Children's Homeの自立した運営を目指して生まれたブランドです。 収益は子どもたちの教育・生活を支える活動に使われています。
-
STUDY&LESSON
講座・稽古
-
-
-
赤城・水道 伝統・芸能2026.03.03(火)
【赤城神社】日本現代舞踊 ばさら舞 ー オーセンティックでモダンな「日本の美」を踊る
日本現代舞踊 ばさら舞の体験お稽古です。 日本現代舞踊 ばさら舞 ー 和扇子(舞扇子)の魅力と、日本の舞踊を現代的に再解釈して踊っています。 和扇子の「曲使い」、上方舞の畳半畳あれば舞うことができるというミニマムでゆっくりとした息遣い、そして西洋のダンスのエッセンスとテクニックを融合し、ダンスのスピード感やターンを取り入れています。 YouTube|ばさら舞 - Japanese Modern Basara Dance https://youtu.be/EfkM2Ary-Oc 赤城神社は700年以上もの長い歴史とガラス張りのモダンな社殿、伝統と現代が融合した美しい神社です。 女性の願い事を叶えるといわれる赤城姫命(あかぎひめのみこと)が祀られており、その御神域に感謝を捧げるとともに心豊かに日本の美を育みます。 主催:奥野ヤスミン 日本現代舞踊家。 海外でのパフォーマンスをきっかけに日本人としてのアイデンティティを考え、しなやかにしたたかに、オーセンティックでモダンな「日本の美」を踊る「ばさら舞」を創始。
-
-
-
-
神楽坂下 講座2026.03.06(金)
【満員御礼】第239回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾
神楽坂大學講座 第239回 神楽坂まちづくりすまいづくり塾 神楽坂よもやま話シリーズ 第175回 音楽の楽しみ ~My Crossroads 語り手: 方喰 浩(かたばみ ひろし)さん クロサワ音楽教室講師 開催日時 : 2026年 3月 6日(金) 19:00 ~ 21:00 会場 : 神楽坂コモンズ 1st ( 神 楽 坂 3-2 本多横丁 中ほど) 最寄り駅:JR・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋」、東京メトロ「神楽坂」、都営地下鉄「牛込神楽坂」 《語り手の経歴》 ・1981年生まれ。 ・13歳の頃よりギターを始め、甲陽音楽学院 在学中より演奏関係の仕事を始める。 ・カワイ音楽教室講師資格取得。 ・クロサワ音楽教室 ギター・ウクレレ講師就任。 ・渡米中Pat Martinoに師事、Master Class、 Private Lesson受講。 その後も交流を深めた。 ・アーティストサポート、ミュージカル演奏、 レコーディング、ワークショップ、教則本執筆などを 行いながら長年音楽レッスンに携わっている。 ・自己の演奏活動を続ける傍ら、ウクレレワーク ショップも定期的に開催。 《講演の概要》 ●20年以上音楽講師を続けて来た中で自身の 経験と音楽の魅力を語ります ●憧れから始まり、好きな音楽が仕事へ ●自身の音楽歴から出会った方達との交流、 アメリカで学んだ事。 ●ギターの演奏と音楽を聴きながら今後の展開 まで思うままに語りつくしたいと思います。 ●皆様のご参加をお待ちしています。 ※お申し込みは、3月2日までにメールで! ■ 定員:20名程度(申込み先着順) * 必ずご予約ください ■ 参加費:1,000円 ■ 主催:NPO法人粋なまちづくり倶楽部 ■ 協力: 神楽坂コモンズ1st ■ お問い合わせ:粋なまちづくり倶楽部 事務局 ・お申し込み先メールアドレス:ikimachi.setsumei@gmail.com
-
-
-
-
赤城・水道 趣味2026.03.07(土)~07.05(日)
【事前申込制】第4回 赤城神社で絵を描こう! お絵かき教室&コンクール
「赤城神社で絵を描こう! お絵描き教室&コンクール」 楽しい絵画の冒険へ! 想像力をかきたて、創造力を育むアート体験にご参加いただけます。人気のお絵描き教室ですので、お早めにお申し込みください。今年のテーマは「私の好きなたべもの」です。講師は昨年に引き続き、ラメ彩輝画家 滝沢彩輝先生。みなさんの個性あふれる作品を楽しみにしています。 また今年は、「神社の雰囲気にあった絵」というテーマで、全国から一般募集も行いますので奮ってご参加ください。 ◆開催日 2026年 3/7(土)、4/25(土)、5/23(土) 各日 ① 10:00受付 10:30開始〜12:00(最終入場11:00) ② 13:00受付 13:30開始〜15:00(最終入場14:00) 作品完成次第終了。退出自由。 ◆会場 赤城神社 参集殿(あかぎホール) ※会場は変更になる場合があります ◆定員 各回70名(先着順) ◆参加費 お子様 お1人につき1,500円(作品の返却費を含む) ◆参加資格 4歳から小学生まで お申込みフォームはこちら ◆ご持参いただくもの クレヨン・色鉛筆(絵の具・マジック不可)。 画用紙は用意します。 ◆作品投票 参加作品は境内に展示しますので、気に入った作品に投票してくださいね。 投票期間:2026年 6/1(月)〜6/19(金) ※掲示作品は、後日郵送にて返却いたします ◆表彰式 開催日時:2026年 7/5(日) 13:00〜 ※受賞者には事前にご連絡いたします ◆一般募集 内容:お絵描きコンクール一般部門 対象:中学生以上 参加費:無料 テーマ:神社の雰囲気にあった絵 出展方法: ・B4画用紙、横向き指定に描いた絵を郵送にて提出 ・裏面に、住所、氏名、電話番号を記入してください。 ※原画のみ、コピー不可。画法自由、平面図。コラージュなど立体作品不可。 ※絵の返却はいたしません。 郵送先:〒162-0817 東京都新宿区赤城元町1-10 赤城神社 提出締切:2026年5月20日(水)必着 掲示期間:2026年5月23日(土)より <開催概要> 主催:赤城神社で絵を描こう!実行委員会 後援:新宿区、新宿区教育委員会、新宿区箪笥町管内町会連合会 お問い合わせ:赤城神社で絵を描こう!実行委員会 委員長 赤木(携帯090-2176-6187)(メール:kentarouakagi@gmail.com)
-
-
-
-
飯田橋界隈 講座2026.03.14(土)
坊っちゃん講座 第12回「反粒子の物理学」
坊っちゃん講座 ■第12回 2026年3月14日(土)15時00分~16時30分 【オンライン開催】 「反粒子の物理学」 東京理科大学では、謎の解明やその応用研究において世界をリードしている研究者が高校生・中学生向けにわかりやすく語る公開講座「東京理科大学 坊っちゃん講座」を2018年9月から開講しています。 講義概要:こちら これをお読みになる皆さんは「反粒子」という言葉をお聞きになったことがあるでしょう。反粒子は想像上の粒子で実際の世界には存在しない、と思っている方も多いかもしれません。ですが反粒子が存在することは100年近く前に英国の物理学者ディラックによって予言され、米国の物理学者アンダーソンによって実際に発見されています。最近では反粒子からなる反物質の世界がどうなっているのか、少しずつ解明されてきています。 電子の反粒子は陽電子と呼ばれます。幸い、陽電子は比較的簡単に得ることができ、基礎物理学の研究だけでなく産業や医療にも利用されています。この講座では、応用研究にも触れながら、反粒子、特に陽電子の面白さを語ります。 理学部第二部 物理学科 教授 長嶋 泰之 申込締切:2026年3月13日(金)午前9時 ※本講座はオンラインで実施いたします。 ※MAP上には「東京理科大学」が表示されておりますが、実際に会場として使用されるわけではございません。 あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 お申込みフォーム https://www.tus.ac.jp/mse/20250314/
-
SPECIAL CONTENTS
特集
SHOPPING
ショッピング
-
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 神楽坂華づくし神楽坂華づくし385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 酔いどれネコ酔いどれネコ385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 道具とネコ道具とネコ385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ ぼたんぼたん385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 一富士二鷹一富士二鷹385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 水引セット水引セット385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 拝啓、ぽちねこ様拝啓、ぽちねこ様385円(税込) -
- オススメ
- オススメ
ポチ袋3枚セット ❘ 月夜のネコファミリー月夜のネコファミリー385円(税込)
LIVE NEWS
ライブニュース