矢来町にあるセッションハウスの専属ダンスカンパニー、マドモアゼル・シネマが誕生して30年。コンテンポラリー・ダンスという言葉が、国内ではまだなじみの少ない時代から、劇団を率いてきた伊藤直子さん。主宰者として、振付・監督役として、時に迷い、時に手探りで、今という時代と向き合いダンス表現を切り拓いてきました。
その30年を超える足跡を振り返ると、日本と世界に架けたダンスの架け橋が見えてきます。




矢来町にあるセッションハウスの専属ダンスカンパニー、マドモアゼル・シネマが誕生して30年。コンテンポラリー・ダンスという言葉が、国内ではまだなじみの少ない時代から、劇団を率いてきた伊藤直子さん。主宰者として、振付・監督役として、時に迷い、時に手探りで、今という時代と向き合いダンス表現を切り拓いてきました。
その30年を超える足跡を振り返ると、日本と世界に架けたダンスの架け橋が見えてきます。

伊藤 直子 様
マドモアゼル・シネマ 代表
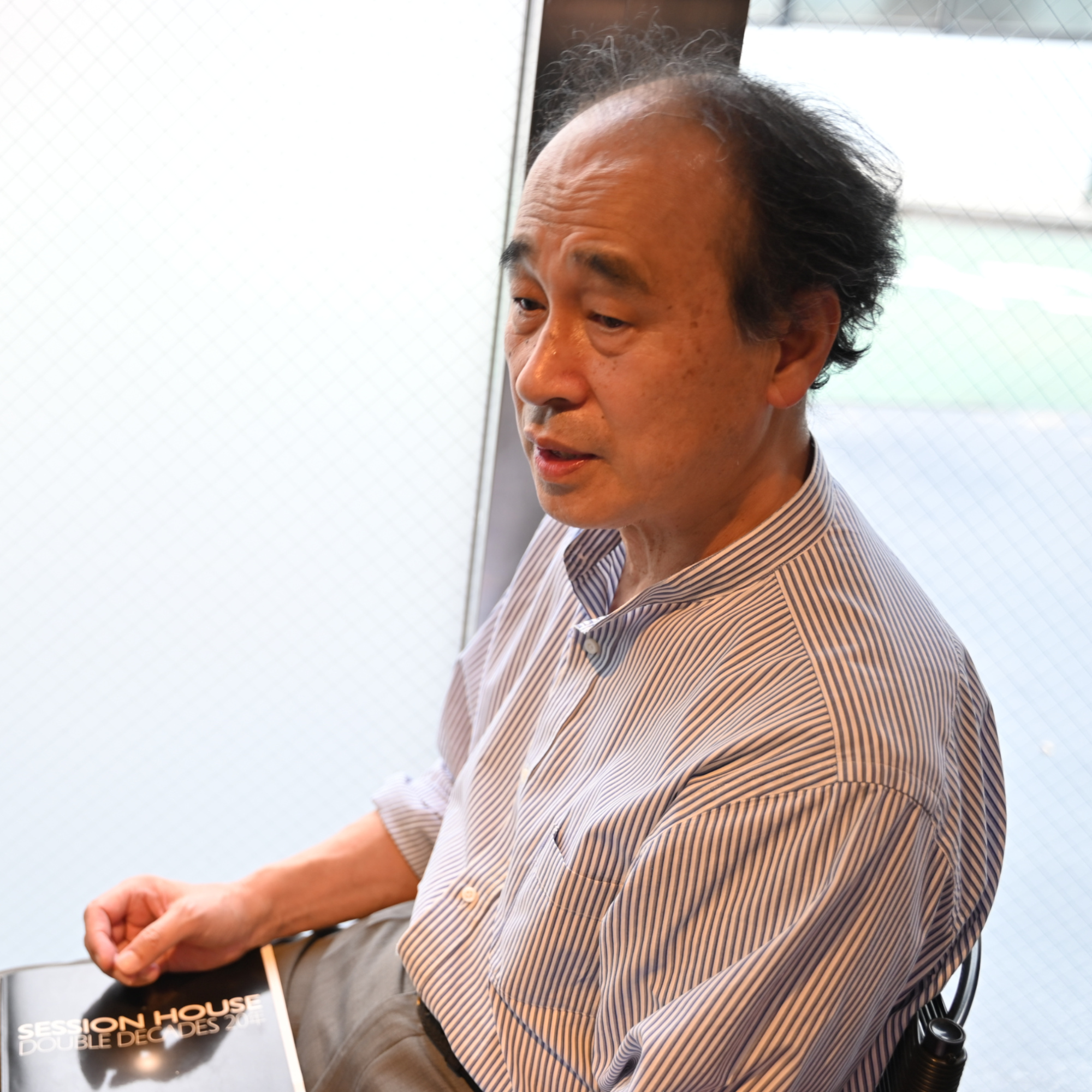
長岡 弘志
かぐらむら編集長
―― 26歳の時にダンスと出会ったとお聞きしていますが
結婚はしていたのですが、仕事を探していたんです。一生続けられる仕事を。私は鹿児島で生まれ育ったので、結婚したら女性は家庭に入るものだと考えていたのですが、結婚相手が女性も職業をもって自立すべきだというのです。ならば、私になにができるのか、一生できる仕事を探してみようと。はじめはフラワーデザインとか、いくつかの仕事に挑戦してみたのですが。
―― それまでは、ダンス経験がなかったのですか?
中学校では器械体操で、高校の途中から新体操をやっていました。卒業後はディスコのような場所で踊っていました。これらは、自分が楽しむためのダンスです。目立つとか、人を惹きつけるとか、目的は楽しみです。ある時、知り合いの誘いでモダンダンスの公演を観に行って、これを仕事にしようとそのダンサーの稽古場に行きました。練習を重ねてから踊るということの素晴らしさにすぐに目覚めました。それまでの私のダンスは、ただの発散でした。それが表現というものに変わった時、ダンスの虜になってしまいました。26歳の頃だと思います。
―― はじめての舞台デビューは?
モダンダンスを習って2ヵ月ぐらいで、すぐに公演に出させてもらいました。その時のことは、いまも鮮明に覚えています。「黒人霊歌」で踊る内容でした。私の出番は最後のほんの数分だったのですが、待っている間にどんどん化粧が濃くなって、がまんにがまんを重ねて舞台に飛び出すのですが、その飛び出す時のタイミングを、その経験を、先生は私にさせたかったのですね。いま考えてみますと、それがピタッと私に合ったんです。

―― すごい集中力だったんですね。
人間は集中するのが好きなんです。だんだんと追い込まれて行って、それを一気に解き放つタイミングが大切です。誰でもそのタイミングが合うと踊れると思いますよ。私は、そのことを教えてくれた先生の劇団で約15年間ダンスを学びました。そこは、渡辺モダンダンス・カンパニーというところです。いろいろな公演も経験いたしました。たとえば、当時六本木にあった小劇場では、舞台いっぱいに竹を運び込み、行燈だけの灯りで踊るとか。田中泯(注1)さんは、その行燈に頭をぶつけながら踊り、私たちは着物を着て、天井から吊るした白いヒモをただひたすら上っていくのです。前衛的な表現なのですが、日常からの異体験が魅力的で、気づいたら15年が経っていました。その面白さは、すべての日常を捨て去っても悔いなし!といった思いでしたね。
(注1:田中泯。独自のスタイルで世界的に知られるダンサー、俳優)
―― それで興行的には大丈夫だったんですか?
もちろん赤字続きの舞踊団でした。まったく売れていない舞踊団で、出演費もままならない、逆にお金は出ていくばかり。公演のたびにも、費用の捻出に努力しました。みんなで先生にお支払するお金をなんとかしようと。でも、そういうことが少しも苦にならなかったから、おもしろいですね。

―― セッションハウスをつくるきっかけは何でしたか?
孝さん(注2)の父が亡くなられて、矢来町の家を立て直そうとなって。でも、ただ新しい家を建ててもつまらない。それなら、住居にダンスの発表の場を兼ねた建物はできないだろうかと。そこで出会った建築家が提案してくれたのは、地下をスタジオに、2階部分は売り出すことで、持ち出しなく建てられる案でした。ところが、あとで気づいたのですが、照明や音響など本格的な設備の予算がはいっていなかった。やる以上は本格的なものがほしい。それで見積りをしなおしたら、いきなり6000万円の追加となりました。本当に驚きました。返せる自信も目途もないまま、迷いに迷って、設備はあきらめるべきか悩んでいたら、そんな無謀な計画を立てるなら縁を切るとまで、親戚からは言われたぐらい。でも結局、夢を捨てられなかっですね。
(注2:伊藤孝氏、セッションハウス代表)
―― 厳しい状況での決断だったのですね
そうなんです!スタジオをつくってからは、本当に大変でした。妹と二人でやっていましたが、私が53歳の時にもう、これ以上は二人ではやっていけないと思い、孝さんに、運営を一緒にやってほしいと頼みました。長年報道の畑で働いてきた彼は、もうすぐ定年という時でしたが、なんとか引き受けてくれました。それから息つくひまなく30年(融資を完済するまで)夢中で活動してきました。孝さんが退職してから、82歳ぐらいまでの時が一番苦しかった。特にコロナがあと1か月早くても返済はできなかった。本当にぎりぎりでやってこれたのです。


―― マドモアゼル・シネマの誕生は、スタジオができてから何年後?
3年後からです。何の自信もあてもないままセッションハウスをスタートさせましたがやはり厳しかったです。自転車操業でやっていけるまでに7年間かかっています。当初はバレエやダンスの教室が経営の中心でしたが、3年目に志をもった若い女性で熱心な人たちが集まって、レジデンス・カンパニー(座付き劇団)をつくろうということになり、マドモアゼル・シネマを立ち上げました。稽古と公演を重ねていくうちに、あっというまに10年、20年。2023年でマドモアゼル・シネマの30周年を迎えました。
