神楽坂が大好きな人の[神楽坂 de かぐらむら]


|
茅の輪をくぐり終われば、すぐそこは七夕の季節。
そろそろ神楽坂でも、願い事の笹竹が飾られはじめます。 そんな季節の風物詩を楽しみながら、週末、神楽坂のまちを歩いてみませんか? 実は神楽坂。ちょいと横丁の路地を入れば、あの有名な文豪たちの逸話、こんな歴史のこぼれ話がたくさんあるのですよ。 さて。そんな神楽坂さんぽにもってこいの、新しいまちガイドを「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」さんが作ってくれました。 日本文化に深い理解を持つロバート キャンベル氏が、神楽坂の伝統芸能・文化にまつわるスポットを訪問して魅力を大いに語り、神楽坂に縁が深い落語家の古今亭菊之丞さん、講談師の神田織音さんが、まちの見所を歴史ガイドしてくれてます。 これを観るだけで、神楽坂のまちがぐっと面白くなりますよ! |
|
神楽坂まち舞台・⼤江⼾めぐり2022 アンバサダーメッセージ
「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2022」アンバサダーにロバート キャンベル氏が就任。桜が満開の赤城神社から、「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり」の魅力を語られています。宵闇に灯る美しい竹あかり、津軽三味線パフォーマンスや邦楽囃子などの路上ライブ、毘沙門天善國寺・講釈場の義太夫節や講談の語り芸、神楽坂の路地や横丁で新内を流す姿、神楽坂と意外な関わりのある城端曳山祭(じょうはなひきやままつり)の庵唄や、赤城神社の夕暮れライブなど、過去の見所映像も紹介されています。 |
|
ロバート キャンベルの神楽坂探訪① 矢来能楽堂
国登録有形文化財の矢来能楽堂を訪問。能楽師の観世喜正氏が、能楽堂の歴史から匠の技が生かされた能舞台の構造や、ほかの能楽堂では見られない貴人口の梅の花などを紹介されています。 そして、桜が咲き誇る京都の嵐山を舞台にした仕舞「嵐山」を披露。春の盛りを寿ぐ、蔵王権現の勇壮な舞をお楽しみいただけます。 |
|
ロバート キャンベルの神楽坂探訪② 宮城道雄記念館
宮城道雄という名前に聞き覚えがあるひとは多いでしょう。そう、お正月によく流れるあの有名な『春の海』の作曲者です。その宮城道雄ですが、生前、神楽坂に住んでいたのをご存知でしたか? 波乱万丈な生涯 8歳で失明した宮城道雄は生田流に入門し、わずか11歳で免許皆伝となりました。14歳で作曲した『水の変態』を、伊藤博文に認められて後援を約束されるも、博文は暗殺されてしまいます。 その後、25歳でデビューし、楽器の改良や新楽器の考案、西洋音楽の要素を日本音楽に導入し、日本音楽の発展に大きな足跡を残しました。 1932年、フランスのヴァイオリニスト、ルネ・シュメーと名作『春の海』を共演し、世界的な名声を得て、海外でも活躍いたします。しかし1956年に列車から転落し、その生涯を終えました。 そんな宮城道雄が愛用した品々、考案した楽器や輝かしい足跡を集めたのが、宮城道雄記念館です。それらが、キャンベル氏の知見によって紹介されています。 また、孫弟子の岡村慎太郎氏から往時を忍ばせる逸話と、箏曲『ロンドンの夜の雨』の演奏を聴くことができます。 この曲は、海外公演の合間に立ち寄ったロンドンで、宮城道雄が作曲したもの。さまざまな雨の姿を、情緒たっぷりに描いている曲を聴きながら、宮城道雄の生涯に思いを馳せてみませんか? |
|
ロバート キャンベルの神楽坂探訪③ 漱石山房記念館
文豪・夏目漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じたまち、新宿。晩年の居の跡地に建つ漱石山房記念館を、紹介したのがこの映像です。 神楽坂を愛した漱石の暮らしぶり 吉住健一新宿区長の案内で、客間やベランダ式回廊、随筆『硝子戸の中』を執筆した書斎など、漱石が暮らした空間を再現したエリアをめぐります。当時の玄関の場所、漱石が夕涼みを楽しんだ木陰、直筆草稿や、『吾輩は猫である』の初版本などの、漱石がデザインした書籍の数々……。きっと新しい発見がありますよ。 |
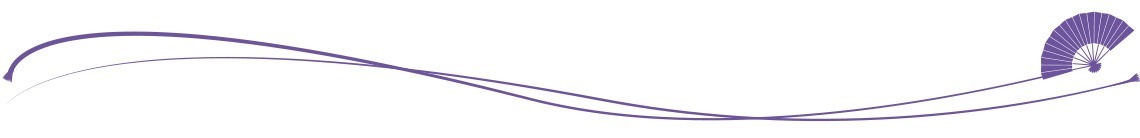
|
落語家古今亭菊之丞による名所旧跡スポットガイド
江戸の話芸で語られる、神楽坂の歴史。若旦那と幇間の会話の妙で、するすると楽しく聞けちゃいますよ。
|
|
名所旧跡スポットガイド「毘沙門天善國寺」
徳川家康が開基した善國寺は、江戸後期に麹町から移転してきました。江戸時代より「神楽坂の毘沙門さま」と親しまれ、泉鏡花の作詞した『ひと里』の中でも、「毘沙門様は守り神」と繰り返し唄われています。
|
|
名所旧跡スポットガイド「光照寺」
上州(群馬県)赤城の豪族大胡氏が築いた牛込城の跡地に、光照寺が神田から移転してきました。このお寺には、新宿区指定(登録)有形文化財が多数あります。
|
|
名所旧跡スポットガイド「圓福寺」
虎退治の伝説で有名な、戦国時代の武将 加藤清正が建立したとされる圓福寺の紹介です。圓福寺は徳川家 大奥ゆかりのお寺でもあります。
|
|
名所旧跡スポットガイド「赤城神社」
鎌倉時代に牛込に移住した大胡氏が、本国 上州(群馬県)の赤城神社を分祀したと伝わります。「赤城大明神」として江戸の三社に数えられ、牛込の鎮守として信仰を集めました。
|
|
名所旧跡スポットガイド「寺内公園」
寺内公園は行元寺という大きな寺の跡地です。江戸時代、江戸中をわかせた、百姓による仇討ち事件が、行元寺の境内でありました。そののちに花柳界発祥の地となり、寺内公園となりました。
|
|
名所旧跡スポットガイド「神楽河岸と軽子坂」
江戸湾と続いていた神楽河岸には、多くの荷船が着き、ここで物資の荷揚げを行いました。荷揚げした品を軽籠(かるこ)を背負って運ぶ人足を「軽子」と呼びました。
|
|
名所旧跡スポットガイド「芸者新道」
かつてこの通りは多くの芸者衆が近道として使っていました。特に料亭が始まる午後の6時と8時ごろに集中していたため「ロクハチ通り」とも呼ばれていました。
|
|
名所旧跡スポットガイド「東京神楽坂組合・見番」
東京六花街と言われるなか、坂あり路地あり迷路のような地形にある神楽坂 花柳界は、今も健在です。その拠点ともいう場所が「見番」です。どこからともなく流れてくる、風情ある三味線の音色。戦前の往時には、600人を超える芸者衆で栄えました。
|
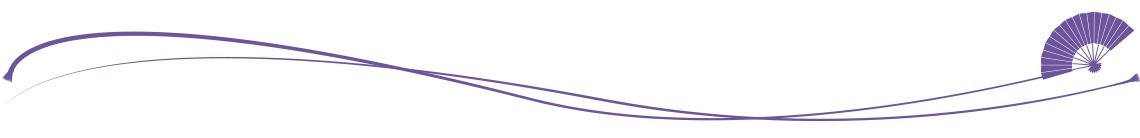
|
講談師 神田織音による漱石ゆかりのスポットガイド
夏目漱石が散策した神楽坂を、講談調で紹介されています。
|
|
漱石ゆかりのスポットガイド「毘沙門天善國寺」
縁日発祥の地とも言われる毘沙門天善國寺は『坊ちゃん』にも登場しています。近くの洋食屋「田原屋」や文具店へ、漱石はよく訪れました。
|
|
漱石ゆかりのスポットガイド「地蔵坂・藁店」
坂上にある光照寺の子安地蔵にちなんで地蔵坂とつけられました。また藁を扱う店があったので、別名藁店(わらだな)とも呼ばれていました。この坂にはかつて和良店亭という寄席があり、落語好きの漱石は足繁く通っていました。
|
|
漱石ゆかりのスポットガイド「寺内公園」
神楽坂花柳界発祥の地。かつてたくさんの置屋があり、柳家金語楼や勝新太郎など、芸能に縁のある人も多く住んでいました。漱石の随筆にも、この界隈は登場します。
|
|
漱石ゆかりのスポットガイド「軽子坂」
軽子坂を下った先の神楽河岸には、かつて濠と共に荷揚場や船着場がありました。漱石の随筆『硝子戸の中(うち)』に、姉の話として登場します。
|

|
講談師 神田織音がご案内 神楽坂の芸能・文化ガイド
神楽坂の芸能・文化スポットを、臨場感たっぷりな講談調で紹介されています。 |
|
神楽坂の芸能・文化ガイド「矢来能楽堂」
★戦災で焼失後の昭和27(1952)年に再建された本格的能舞台を備えた能楽堂で、国登録有形文化財です。観世九皐会の拠点として、能楽の定期公演をはじめ初心者向け普及公演にも力を入れ、伝統芸能の普及と維持に活用されています。
|
|
神楽坂の芸能・文化ガイド「宮城道雄記念館」
宮城道雄が晩年の26年間居住した地に建っている記念館です。展示室や資料室のほか、作曲や執筆に使用した国登録有形文化財の書斎「検校(けんぎょう)の間」が当時のままに残されていいます。
|
|
神楽坂の芸能・文化ガイド「漱石山房記念館」
夏目漱石が亡くなるまでの9年間を過ごし、数々の名作を生んだ「漱石山房」の地に開館した記念館です。
|
|
神楽坂紹介の映像はいかがでしたか?
この週末はぜひ神楽坂へお越しいただき、まちに残る歴史をお楽しみください。 |
DATA:「神楽坂まち舞台・大江戸めぐり2022」2022年5月21日(土)~5月22日(日)
主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京/NPO法人粋なまちづくり倶楽部
助成・協力:東京都
共催:新宿区
後援:一般社団法人新宿観光振興協会
協力:東京神楽坂組合/毘沙門天善國寺/赤城神社/観世九皐会・矢来能楽堂/宮城道雄記念館/漱石山房記念館
株式会社粋まち/神楽坂通り商店会/神楽坂商店街振興組合/セッションハウス/志満金/THEGLEE
SEION 神楽坂店/光照寺/圓福寺/東京都消費生活総合センター/あずさ監査法人/東京理科大学
第一勧業信用組合 神楽坂支店/熊谷組/ロングランプランニング/オフィスヤマグチ/マインド
