追悼
さようなら
キイトスカフェ
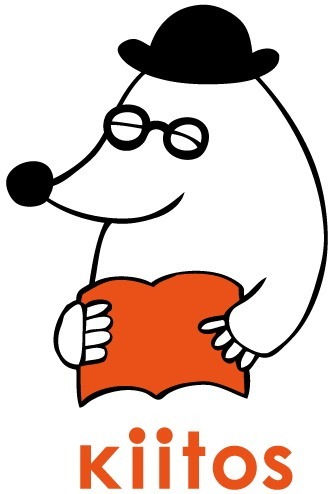
“Pax intrantibus, Salus exeuntibus=歩み入るひとに安らぎを、去りゆくひとに幸せを”
| 神楽坂の本好きのオアシス、あるときは食堂、またあるときは隠れ文化サロン…18年間様々な物語を紡いできたキイトス茶房が、2019年9月30日、静かに閉店。それから間もなく、10月18日、店主の清水敬生さんが亡くなりました。 ここ数年の闘病のことは、マスター自身がいつもジョークのように語りながら、といって何が変わると言うこともなく、いつも笑顔でマイペースにお店に立ち続けていました。だからまさかこんな突然の(ように演出してみせた)エピローグはやはり、人を驚かすことが大好きな夢想家の仕業に違いありません。 私とキイトスの出会いは18年前。 「つい先日、面白そうな喫茶店が出来たんだ。」 神楽坂の大先輩に連れられて来たのがはじまりでした。当時私は駆け出した途端にズッコケていたイラストレーターで、それまで全く縁のなかった神楽坂のまちづくりにうっかり足を突っ込んでしまったばかり。そんな得体の知れない若造に、お店の立て看板とメニュー表を依頼してくれました。その時に誕生したキャラクターが『キイトス君』。本とともに穴(店)に籠もっているモグラは、もちろんマスターがモデルです。 以来18年間、神楽坂という色々な意味で奥深い街に何度も呑み込まれそうになりながら、この街でチャレンジした色々な企画を、マスターはいつも無条件に応援してくれました。 キイトスのおかげ。ありがとう=Kiitos(フィンランド語でありがとうの意)。 そんな想いの人が、このお店にはいっぱい集ってきていました。 風のように去ってしまったマスターに変わって、みなさんにキイトス茶房のおしまいのお知らせをさせていただきます。 おかめ家ゆうこ(イラストレーター/造形作家)
|

| ちょっとさよなら、清水さん 2007年2月12日、初めてキイトス茶房に行ってからもう12年半以上の時間が経っているとは俄かに信じがたい。全員が初対面という21人が恐る恐る階段を上って戸を少しばかり開けて覗き込み、あ、やっぱりほんとにやるんだ!と足を踏み入れてきたことが甦る。 今や昔のものになっているらしいmixiを通して、高齢者及び高齢者予備隊が怪しげな催しであると理解していた「オフ会」なるものに集まったのには勿論それだけの理由があって、ビデオはともかくDVDなどというものもそれほどポピュラーなメディアではない時代、故人の遺志もあって観ることが叶わなかった古今亭志ん朝さんの高座姿を、個人が録画していたTV番組を持ち寄って見ようじゃないかという話が瓢箪から駒のように飛び出し、志ん朝さんの住んでいた矢来町の隣の箪笥町にキイトス茶房といううってつけの場所があるというのでお借りすることになったのが、清水さんとの長いお付き合いの始まりだった。他の開催場所など探す必要のないお付き合いが続いて、11月16日に66回目の『志ん朝いごくを観るの会』をすることになっていたのだったが、それを迎えることなく清水さんは逝ってしまわれた。 栢野由紀子(『志ん朝いごくを観るの会』長屋連年寄)
P.Sあっち側でキイトス茶房、開いておいてくださいね。仲間のうちで既にお手伝いできるに人も何人かいるし、我々もおっつけ駆けつけますから。 |

| 14年前のMさんの言葉 『かぐらむら』22号(平成17年10・11月号)でこんな特集を掲載したことがあった。 特集のタイトルは、“神楽坂好み”の時間。 まちに人格があるならば、利休好みのように“神楽坂好み”というものがあるかもしれない。しかし、それを表現するのはきわめてむずかしそうだ。そこで日頃小誌『かぐらむら』の編集や取材に携わっているスタッフの一人ひとりに、自分にとっての勝手気ままな“神楽坂好み”の時間を語ってもらった。そして写真も各自自由に撮ってもらうことにした。参加して原稿を書くことになったのは9人、平均年齢は35歳、ほとんど未婚者。さて、どんな好みの時間がでてくるのか、お楽しみに。 そして筆頭一番にあがって来た原稿が、当時30代中頃、独身のMさんの原稿だった。それは「キイトスカフェ」について書かれていた。以下全文Mさんの文章である。 号泣できる場所―キイトスカフェ 「ぼんやりする贅沢」 神楽坂はひとりが心地よい町だ。本を読んだり、町ゆく人々を眺めたり、ぼんやりと考え事したり。そういう時間を過ごしていると、突然涙が溢れてくることがある。心のバリアがボロボロと剥がれていくのだろうか。誰にも邪魔されず、心の動くままに過ごせる時間は、とっておきの贅沢だ。 「本に出会う幸せ」 休日、遅めのランチ。キイトスカフェで本を読みながら過ごすこの時間はまさに至福のひととき。この店に来ると、たくさんの本に出会える。座席にも、背後の本棚にも、床に置かれた籠にも、読んでみたかった本がある。店内が静かなのもいい。若い夫婦が一言もしゃべらずに思い思いの本に没頭する姿はなんとも好ましい。もう、本好きにはたまらない空間だ。 「号泣できる場所」 先日、ここで出会った本を読んで号泣してしまった。花嫁衣裳をあつらえてくれた母との思い出を綴ったエッセイだった。自分が結婚した時のことや、お腹にいる赤ちゃんのこと、数々の思い出がこんなにも鮮明によみがえる場所は他にない。とりとめもなく溢れてくる感情を、日当たりのいい窓際の席は、いつも黙って受けいれてくれる。(み) この文章を書かれた後、彼女はタウン誌を卒業、そして結婚。当時の仲間に聞けば、いまは神楽坂を離れ、二児の母となって忙しい日々を送っているという。キイトスカフェの店主、清水敬生さんが永眠されたこと、お店が幕を降ろしたこと、伝えてあげたいがいまの彼女の住所を私は知らない。 長岡弘志(サザンカンパニー)
|

| キイトス・コミューン(=通称キイトス会) 私がキイトス茶房さんに最初に伺ったのは、自分の創業前だと思うので、15年以上前でしょうか? 当時、ごく近所に住んでおり、一人暮らしで外食が多かった私は、キイトス茶房が、雰囲気の良い“ブック・カフェ”でありながら、同時に、いつ行っても暖かい“ご飯メニュー”が食べられることに、すぐ気がつきました。 又、お話好きのマスターは、メニュー開発にまつわる家族のエピソードや、ユニークな丼メニューの名前の由来、食材の仕入れ話なども、良くお話してくれたので、私は食べる度にそれを思い出し、なお一層味わい深く感じたものでした。キイトス茶房のメニューのひとつひとつに人間的なエピソードが多い事は、明らかに他店との大きな違いでした。そして、マスターが、大変な読書家であり、映画にも並々ならぬ情熱を向けていたことは、店の看板の副題である『ブック・シネマ・ギャラリー』の示す通りですが、“インテリでロマンチスト”であったため、前職の司法書士事務所を早期にやめ、第二の人生を、カフェのマスターに転身した事は、広く知られています。 店内のテーブルと椅子は、全て特注のアンティーク・デザインで、店の設計図から大きさや配置も考慮して、家具職人と相談して造り、発注から納品までに時間がかかったせいで、開店時期をずらさざるを得なかったエピソードなども、マスターが店に注ぐ情熱と愛情を感じさせ、お客である私たちにとっても、特別な場所と感じられました。 店の壁には、ご自宅から持ち込んだ多彩なジャンルの本と映画、そして開店後に収集した分も合わせて書棚にぎっしりで、背表紙を見ているだけでも目がまわるほどの乱読振りです。映画やお料理にまつわる本もとても沢山ありました。そして、クラシックの音楽を流す愛用の大きなスピーカーは、まだお金の無い時代に購入したので、絶対に手放したくない、とおっしゃっていました。この茶房は、マスター本人にとっても、愛着に満ちたものに囲まれたカフェだったと思います。 “心とお腹を満たすカフェ”という店のキャッチコピーそのままに。 ところで、男性の常連客にとっては、マスターは、“寡黙でシャイな人”だったそうです。―びっくりです!たぶん、多くの女性客にとってマスターは、“饒舌で面白い人”という印象の方が、強かったのではないでしょうか?マスターは、前職は法律家で、政治や経済の先生のような人でもありながら、プライベートでの失敗談(初恋で盛大にふられた話など)なども、面白おかしく聞かせてくれる、博識でおしゃべりが面白い人、という印象でした。そういった会話が楽しいが故に、わざと空いていそうな時間を狙ってお店に通い、厨房近くの席に陣取ったものです。 又、マスターのもうひとつの特徴として、とても面倒見が良く、困っている人がいると助けずにはいられないようなところがありました。実際、神楽坂で起業した人で、マスターのお世話になった人はかなりの人数にのぼるのではないかと思います。前職の時なら有料でうけるような相談や案件を、無料で非常に親身になって助けてくれていました。 これは、茶房の奥の席の壁横に常にかかっていた、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」が、大・小の額縁で2枚もあったことを思うと、「正にこれこそが、キイトスさんの本質」、という気がしてなりません。―弱気を助け、権力に物申す人でした。 そんな面倒見の良いインテリのマスターの元には、当然のように沢山の多才な人たちが集まり、満を持して、2008年の11月に、マスター本人が「キイトス・コミューン」と名づけた、茶房の場所を提供しての“異業種・異人種交流会”第1回目がスタートしました。それから11年目を迎えた今年の11月、茶房はなくなりましたが、このコミューンから派生した各種文化会とそれを支える有志が集い、2019年、11月、キイトス・コミューン(=通称キイトス会)が、新たに発足しました。マスターには、長年、茶房で暖かく迎えて頂きながら、その生き様をも見させて頂きました。とても大きな存在でした。これからは私達が、その遺志を受け継ぎ、広げる活動をすることが、何よりの手向けと信じます。 キイトスさん。ありがとうございました! これからも見守って下さい。又会いましょう! 藤沢甲斐(インド・アラブ民族衣装店ジジ)
|

